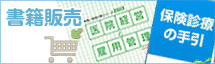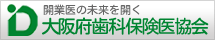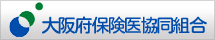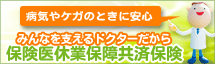作家寄席集め 第46回 石原 慎太郎/恩田雅和
 一橋大学在学中「太陽の季節」を発表、若者たちの奔放な生態を描いて芥川賞を受けた石原慎太郎(1932~2022)は、娯楽小説、サスペンス小説などの分野で作家活動するとともに、三十代半ばからは政治家としての足跡も記しました。
一橋大学在学中「太陽の季節」を発表、若者たちの奔放な生態を描いて芥川賞を受けた石原慎太郎(1932~2022)は、娯楽小説、サスペンス小説などの分野で作家活動するとともに、三十代半ばからは政治家としての足跡も記しました。
石原はその言動とパフォーマンスから政治家としてのイメージが強く残されましたが、最期まで執筆生活は続け、雑誌「新潮」の2022年4月号に遺稿「遠い夢」が掲載されました。この短編小説は、初恋の女性が病死したことを知らされた「私」が葬儀に行き、白い薔薇の花を祭壇に撒き散らすというもので、遺影に向かって香炉を投げつける「太陽の季節」の一節を想起させました。
石原文学にはすでに初期作品から死にまつわる話が一貫していて、2020年に刊行された7つの短編集『死者との対話』には、表題作のほか「いつ死なせますか」「死線を超えて」などが収められていました。その一つが「ある奇妙な小説」と副題された「老惨」で、死期が近いと覚った男のモノローグと会話で綴られる作品です。何人かの故人が実名で出て、中に「俺の腐れ縁だった立川談志が晩年いろんな所に癌が出来てきてしまって最後には声帯をやられて声が出なくなっちまった。それまでもしきりに死にたい死にたいとあちこちで言っていた」と談志についても述べています。
石原は談志とは何回か雑誌対談していて、談志が亡くなる前年の2010年、落語を演じている最中に登場人物が勝手にセリフをしゃべるとぼやく談志に対して、石原は返します。「作中人物が裏切ったり反乱したり勝手に動いたりするの、面白いね。だからそれで立川談志の「死神」なんて聞きたいんだけどね、怖い話だけど。」1989年10月、11月の「新潮」に石原は「自分の身の回りにあったいくつかの、なぜか忘れがたい出来事や人から聞いた話」の「ショートショート」である『わが人生の時の時』を一挙掲載しました。そこの1篇に「死神」があり、落語の「死神」を早くからモチーフにしていたことがうかがえます。
2012年2月、追悼文「さらば立川談志、心の友よ」を雑誌に寄稿した石原は、談志と弟子の親子会をのぞいた際、一席を演じる体力のなくなった談志が「二十分ほどの小噺そのものは卓越したショートショートを繋いで本当にうまいものだった。」と賛辞を寄せていました。ショートショートの共通項により、その時の石原には談志の落語が文学そのものと映っていたようでした。