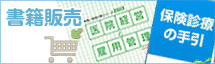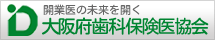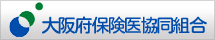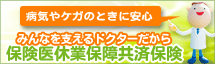作家寄席集め 第44回 瀬戸内 寂聴/恩田雅和
恋愛小説や伝記小説を発表して人気を集めた作家で僧侶の瀬戸内寂聴(1922~2021)は、自立した女性の先駆者として99歳の天寿を全うしました。
寂聴の作家的原点となったのは1962年に雑誌掲載された短編小説「夏の終り」で、彼女が三十代のおよそ8年間、妻子ある不遇な作家と恋愛関係におちいり、あわせてかつての年下の恋人とも付き合うという複雑な経験を描いたものでした。この後に書かれた「みれん」、「花冷え」、「あふれるもの」も登場人物が同じのいわば連作短編で、これらを通して世間的には認められなかった生活を客観視し、文学作品に高めました。
「夏の終り」で、自宅と愛人の家との二重生活を続ける登場人物の印象深いセリフがあります。大晦日に女性主人公が風邪をこじらせて発熱し、床についた際の一言、「元旦は出来るだけ早く来るよ。寄席にでも行こうか」。
岡本かの子、伊藤野枝という激しい生き方をした女性の伝記を主に残した寂聴には、珍しく講談師を書いた小説があります。晩年の二代目神田松鯉を取材して修業時代の苦心談や女性遍歴などを下積みの女性作家が聞き出すという中編小説「花野」(1964年)で、芸人がみな実名で出てきます。作者本人がモデルの聞き役の女性作家は、「落語は聞いても、講談といえば」「聞かず嫌い」で、友人に誘われ講談定席の本牧亭に通い出します。昼席の客数がようやく20人に達したとか、常連のような客がみんな相当な年輩とか、1972年に定席を閉じる前の本牧亭の様子が詳細に語られています。
松鯉の父は二代目神田伯山で、「宋朝水滸伝」などで八丁荒しの異名をとる人気実力者でした。しかし松鯉があまりにバクチ好きだったため、父は三代目を弟子の小伯山に譲り、息子には隠居名で名乗っていた松鯉を二代目として襲名させたいきさつも記されています。
寂聴は「夏の終り」の連作を書き上げた直後、満3年にわたり職人にインタビューする記事を雑誌連載しました。実は二代目松鯉もその記事の一つに取り上げていて、『一筋の道』(1967年)で単行本化した際、「花野」を「創作活動を刺戟されて、改めて小説に書き直した」とあとがきしています。「自分にしかない独自の才能の芽を育て、その開華のために努力してみるという生き方」に引かれたとも述べていますが、それが彼女自身の生涯そのものであったようでした。