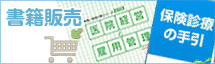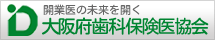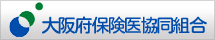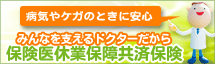作家寄席集め 第43回 古井 由吉/恩田雅和
随想風かつ私小説風な様相を呈しながら非現実的で幻想的な小説作品を多く残した古井由吉(1937~2020)は、人間の内面を見つめる「内向の世代」の代表的な作家と目されました。
 その古井が1999年6月に短編「犬の道」(連作集『聖耳』に収録)を発表し、そこで昭和23年に父親に連れられ初めて新宿末広亭へ行った思い出を綴っています。それから2年と経たないうちに「ラジオの寄席番組を欠かさず聞くようになり、古い落語しか受けつけず、小学生の内から、好きなのは志ん生と柳好と右女助と言うほどになった。」かなり早熟な耳の肥えた小学生だったようです。
その古井が1999年6月に短編「犬の道」(連作集『聖耳』に収録)を発表し、そこで昭和23年に父親に連れられ初めて新宿末広亭へ行った思い出を綴っています。それから2年と経たないうちに「ラジオの寄席番組を欠かさず聞くようになり、古い落語しか受けつけず、小学生の内から、好きなのは志ん生と柳好と右女助と言うほどになった。」かなり早熟な耳の肥えた小学生だったようです。
2006年10月に書かれた短編「野晒し」(短編集『白暗淵』に収録)は、尾方という主人公が小学生の頃から聞いていた噺の一つとして「野晒し」を挙げています。世間の流行に疎い尾方がたまたま入った寄席で聞いた「野晒し」の本来の怪談調から滑稽調に変遷された歴史が語られ、尾方が風邪で寝込んだ床に夜な夜な老女が通う話に替わります。どうやら女は幽霊だったようで、現実と非現実がいつの間にか入れ替わる古井お得意のストーリーが展開されていました。
1976年3月の中編小説「夜の香り」は、アパートで自殺した学生の友人の大倉が第一発見者となっててきぱきと後始末にあたるのみならずその晩から死者の部屋に泊まり込む話です。大倉は他の部屋の主婦たちにも気軽に声をかけ出し、アパートの主のような存在になります。
ここまでのストーリーで、長屋の鼻つまみ者らくだの急死後に訪ねてきた兄貴分が香典を集めさせるという、「らくだ」が下敷きにされていることが知らされます。「野晒し」の30年前に、古井はすでにもう一つの名作「らくだ」を小説の中に取り入れていたのでした。
東京生まれの古井は父の実家のある岐阜県に一時疎開した以外はずっと東京に暮らし、日比谷高校に転校する前の5か月間は独協高校に学びました。
2014年刊行の『半自叙伝』に、その独協高校の「同学年に美濃部君、後の古今亭志ん朝師匠がいた。私と違って本格のドイツ語クラスにいた。」と述べています。小学生時分から落語になじんでいた古井にとっては、後年高名になる名人とわずかでも同学年で在籍していたことは誇らしかったのだと察せられます。
2021年は志ん朝の没後20年でした。そして本年2022年の今月18日は、古井由吉のちょうど3回忌にあたります。