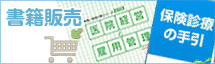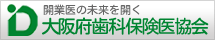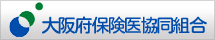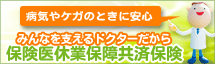心温まる風景画やユーモアあふれる絵本で国際的に知られた画家の安野光雅(1926~2020)が、昨年12月24日に病死したと1月中旬に報じられました。
 島根県津和野町に生まれた安野は初め美術の教師をし、のちに子供から大人まで楽しめる絵本や世界各地の風景を水彩画などで発表して名声を確立しました。
島根県津和野町に生まれた安野は初め美術の教師をし、のちに子供から大人まで楽しめる絵本や世界各地の風景を水彩画などで発表して名声を確立しました。
2001年春、郷里津和野のJR駅前に「安野光雅美術館」がオープン、4千点を超える安野作品が収蔵されて、今年20周年を迎えます。5年ほど前、私は森鷗外の生家と記念館を訪ねた折、安野美術館にも足を運んで、味わい深い作品群に圧倒されました。
その美術館の一角には、安野が出版した絵本、画集のほかに数多いエッセイ集が並ぶ書棚があって、しばらく私はそれらの著作に引き込まれました。そのうちの1冊が、1976年刊行の切り絵と文章からなる『がまの油―贋作まっちうりの少女』でした。「あとがき」には、こうありました。「一冊の本は、と聞かれれば、私はためらわずに、森鷗外の即興詩人と答える。原作のアンデルセンと共に、傾倒した東西二人の作者である。それに私は落語が好きである。そんな私が、柱に頭をぶっつけたりしたら、何ができ上るか。それが、この本であった。」
同郷の文豪森鷗外と先駆的な童話作家アンデルセンを敬愛してやまなかった安野は、落語好きでもあって、タイトルを落語とアンデルセンをモチーフにして付け、本文は鷗外の即興詩人の文体を模していて彼の原点のような本でした。
実は安野の落語好きは筋金入りで、2006年に出された自伝的なエッセイ『空想亭の苦労咄』は、さまざまな古典落語の一節を引用しながら自身のこれまでの生活を振り返るものでした。そこでは文体まで噺家口調にされていて、次のごとく述べられています。「あたしゃあ東京へ出てくる前から落語が好きでしてね、東京へ来てからは主に新宿の末広亭でしたが、よく通いましたな、そこで、すっかり落語にかぶれまして、とうとう落語の言葉でものを考えたりするようになりました。その好きな落語の言葉でしゃべるってぇと、どういうわけか、どんなことでもしゃべれて、楽しい世界へ入って行ける気がするんですな、そこで田舎弁は、一時しまっといて、落語弁で考えようって思うんで、へぇ。」
噺家口調で過去を回想し、まるで新作落語風に仕上げた理由がよく理解できるところでした。