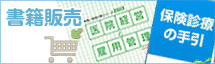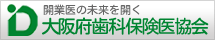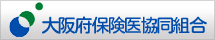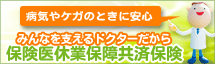2020年の正月映画で周防正行監督の「カツベン!」が公開され、かつて大衆娯楽の王道であった活動写真や活動弁士があらためて話題になりました。
2020年の正月映画で周防正行監督の「カツベン!」が公開され、かつて大衆娯楽の王道であった活動写真や活動弁士があらためて話題になりました。
無声映画は現在、色物として繁昌亭でも時折上映されており、坂本頼光や大森くみこといった若い活動弁士が今風にその話芸を披露しています。
かつての文豪たちはそうした活動弁士に無関心ではいられなかったようで、何人かがいくつかの作品に取り入れていました。
明治末から昭和にかけて活躍した徳田秋声(1871~1943)は、昭和10年に連載した長編小説「仮装人物」で、「『闇の光』、『復活』などもそこで彼女と一緒に見た無声映画であった。」「まだそのころは映画も思わせぶりたっぷりな弁士の説明づきで、スクリンに動く人間に声のないのも、ひどく表情を不自然なものにしていた」などと映画を語っていて、昭和16年の「縮図」では、「弁士の谷村天浪」「土屋といふ弁士」など弁士の芸名まで記していました。
日本の探偵小説の第一人者、江戸川乱歩(1894~1965)は中学生の頃、当時住んでいた名古屋市の御園座で無声映画を鑑賞して感激した文章を残しています。「そのころ著名の弁士兼興行師であった『スコブル大博士』駒田好洋という人が、『ジゴマ』を持って地方巡業をしていたもので、瘦せ型でメフィストめいた風貌の駒田氏が、コーモリの羽根のような黒いインバネスコートの袖をひるがえして、前説をした光景が今も目に浮かぶ。」(「わが青春の映画遍歴」)
映画の説明中の「すこぶる非常」が口癖で自ら「すこぶる大博士」を名乗って人気を博した駒田好洋を、乱歩は実際に見ていたのでした。その影響もあったからか、まだ小説を書く前の24歳の頃、大阪の会社を辞め放浪した後に東京にたどりついた乱歩は、「もう十日もしたら、いよいよパン代もなくなるという土壇場になって、私は活弁になって収入の道を得ようと決心」しました。そこで弁士の江田不識を訪ねましたが、「弁士の前座になつたつて、二三年は無給の手弁当だよ」と言われ、「すごすごと引下つた」のでした(「活弁志願記」)。このように乱歩に、活動弁士を志した時期があったことは意外です。
その乱歩が、後年名探偵・金田一耕助シリーズで推理小説の名作を次々に産み出した横溝正史(1902~1981)を見出します。神戸の実家で薬剤師を務めていた横溝に乱歩が上京を勧めたもので、横溝の方は、大正14年の4月初めて乱歩に会って、「このとき私の運命は決定したのである。もし、このことがなかったら、引っ込み思案の私のこと、いまでも神戸で売れない薬局を経営しながら、しがない生涯を送っていたにちがいない。」(「探偵小説昔話」)と回想しています。
横溝の代表作の一つ「悪魔の手毬唄」は、昭和32年から34年にかけて雑誌連載されました。昭和30年8月の岡山と兵庫の県境を舞台に、土地に伝わる手毬唄の歌詞通りに連続殺人事件が起こり、金田一耕助が事件解決に乗り出すという内容です。この事件には昭和7年に同じ村で発生した殺人事件が関与していて、金田一は前年の6年に村に現れ事件後、姿をくらませた男の行方を追い、つぶやきます。「この昭和六年という年を映画のほうでみますと、そうとう重要な年になっているようです。つまりトーキーがおいおい軌道にのってきて、弁士という職業のひとたちが前途に不安をおぼえはじめたのがそのころなんです。」神戸の活動弁士青柳史郎がこの事件の鍵を握っていて、背景には無声映画からトーキーに移り変わる弁士の不遇時代の始まりがありました。
神戸で生まれ育った横溝には、新開地でなれ親しんだ活動写真や活動弁士が記憶の奥深くにあり、それを作品のモチーフにすることによって、「一番僕の作品では文章の嫌味もなくよく出来た」(昭和37年「宝石」)と評する「悪魔の手毬唄」が誕生しました。