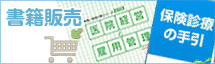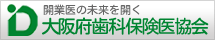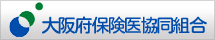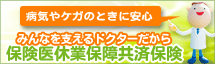作家寄席集め 第45回 松崎 天民/恩田雅和
 新聞記者として大逆事件などを取材したほか底辺の女たちをルポして小説化するなどした型破りのジャーナリストが、明治大正昭和にわたって活躍しました。
新聞記者として大逆事件などを取材したほか底辺の女たちをルポして小説化するなどした型破りのジャーナリストが、明治大正昭和にわたって活躍しました。
岡山県生まれの松崎天民(1878~1934)がその人で、一家破産して京阪を流浪した後、東京の国民新聞の小使になったのをきっかけに新聞社の仕事をするようになりました。
1900年に記者としてスタートしたのは大阪新報で、続いて大阪朝日新聞、東京の国民新聞、東京朝日新聞と14年間で在籍社が目まぐるしく変わりました。その間、大逆事件で刑死する管野スガの法廷の姿や処刑された後の内山愚堂の柩を弟が叩き割った模様などを詳述して、東京朝日の同僚だった石川啄木に衝撃を与えました。
松崎本人は記事にする際、客観視する「新聞記者的態度」とそこに詠嘆を交える「文学者的態度」を試行錯誤し、結局両者を使い分けて人生の探訪者たる「探訪記者」を自認しました。
1912年に雑誌「中央公論」に連載し話題となった「淪落の女」は後者の方で、浅草の私娼窟や長野の芸妓など実際に取材した女たちをルポルタージュ風の小説作品にして発表しました。
1910年在籍社で新聞連載した「寄席印象記」は前者の方で、落語だけでなく文楽、浪花節、女義太夫、講談と当時盛んだった芸能の演者や小屋の事情をリポートしています。このうち銀座の金沢亭を取材したものでは、三代目柳家小さんのことを述べています。「小さんは肥って居る、横町の伯父さんと云った風の態度、既に世に定評あると云ふが、しろうとには判らない」「今の寄席に於て、眞に腹の底から笑へる話を聴かうとするのは、自転車で富士登山を思ひ立つの様なものだと思ふ」。
小さんについて夏目漱石は同じ東京朝日でその2年前に連載した小説「三四郎」で絶賛しましたが、松崎は手厳しく語っていました。
逆に開化期の東京で寄席に出ていたイギリス人の異色落語家、快楽亭ブラックには好意的な批評を寄せています。「話中の人物と人物の対話になると、日本人以上に日本語が巧い」「まるまると脂切って極めて楽天的で、少しも其の屈託らしい面持ちがないのも、見て居て心持ちが好い」。
あらゆる分野を旺盛に探訪していた松崎の寄席報告は、やはり見過ごせないものがありました。