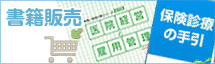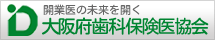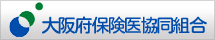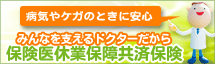山本周五郎
- 2019/4/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第9回 山本周五郎/恩田雅和
人情もの時代小説の第一人者、山本周五郎(1903~1967)の文壇デビュー作は、『文藝春秋』の大正15年4月に発表された「須磨寺附近」です。
 山梨県に生まれ、東京の質店に徒弟で住み込み、戦後すぐから横浜で作家生活の大半を送った周五郎の処女作ともいえる作品が、関西の神戸が舞台でしかも現代ものであったというのは意外でした。
山梨県に生まれ、東京の質店に徒弟で住み込み、戦後すぐから横浜で作家生活の大半を送った周五郎の処女作ともいえる作品が、関西の神戸が舞台でしかも現代ものであったというのは意外でした。
大正12年の関東大震災で質店が被災した周五郎は、関西に避難し兵庫県豊岡の地方新聞社に就職しましたが、すぐに辞めて神戸市須磨区に向かいました。そこに幼友達の姉が嫁いでいたので、止宿させてもらいながら観光ガイド誌の記者の職を得ました。その仕事も4カ月ほどしか続かず、翌年にはもう東京に引き上げてしまいますが、神戸での体験が小説作品に結びつきます。
「須磨寺附近」は、月見山にある友人の姉の嫁ぎ先が夫の米国勤務のため友人も姉と一緒に暮らしていて、そこに転がり込んだ清三の話になっています。休日に三人は六甲山や須磨寺などを散策し、清三は5歳上の友人の姉に淡い恋心を抱きます。ある日、清三は友人の姉に神戸座の芝居に誘われ、勤めの後に勇んで出かけると、そこには見知らぬ男が彼女と親しそうに話していました。清三はただ遠くから二人を見つめただけでしたが、のちにそれが彼女の米国行きを夫の上司と相談していたことと知らされます。
当時22歳の周五郎の文壇出世作に、実際にあった神戸座が重要な舞台になっていました。周五郎が神戸に居た時分、新開地に神戸座が実在しており、小説中のように芝居と映画を見せていました。そこは昭和になって新松竹座と改称され、映画専門館になりましたが、別に神戸松竹座が昭和34年元日から新たにスタート、51年9月の閉館まで演芸場として笑いを市民に提供していました。
「二階の正面の席」「東の桟敷」など松竹座の内部も書きこまれていますので、周五郎はこの時の松竹座に何回か足を運んでいたと思われます。
東京に戻った25歳の折、周五郎はぶらりと立ち寄った現在の千葉県浦安市が気に入り、そこに住まいを見つけて1年余り東京の勤務先まで通いました。その経験が、およそ30年後の昭和35年1月から12月まで『文藝春秋』に連載された長編小説「青べか物語」に生かされることになります。地名は浦粕町ですが、その頃の浦安町をモデルにしていたのは明らかで、洋食屋、旅籠宿などとともに「浦粕亭(寄席)へなにわぶしを聞きにゆこう」など寄席の浦粕亭も出てきます。
さて周五郎本領の時代小説ですが、昭和21年から25年頃に書かれた中短篇には、面白いことに別名のペンネームがしばしば使用されているのに気づかされます。「備前名弓伝」の神田周山は講談師のような名前ですが、「風流化物屋敷」と「ゆうれい貸屋」の風々亭一迷(夫婦ゥテ言ッチメエ)、「人情裏長屋」の折箸蘭亭(俺ハ知ランテー)、「長屋天一坊」の酒井松花亭(酒一升買ッテー)などいかにも戯作者風、落語家風の作者名でニヤリとさせられます。
「長屋天一坊」は確かに「第一席天一坊は大逆犯人のこと」など、小見出しで一席、二席と記す落語仕立てにしていますし、終いの第九席では「並びに事件落着大喜利のこと」と寄席用語の大喜利まで使っています。
「大衆小説を初めて書かせてくれた」山手樹一郎について回想した昭和35年の文に、「三年くらい前に、僕の親しい新人落語家の会が池袋であった時、近所まできたから山手の家を訪ねようと思った」と落語家と親交のあったことも述べられています。周五郎は寄席に馴染んだ結果、親しい落語家が出来、ある面で落語家、または講談師の口調によって時代小説を紡いでいったようです。