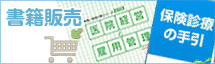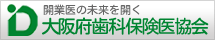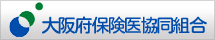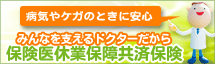志賀直哉
- 2019/1/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第6回 志賀直哉/恩田雅和
小説の神様と言われた志賀直哉(1883~1971)は、学習院高等科に在籍していた頃、義太夫と落語に熱中していました。志賀の明治37年元日の日記に、「久本に吉花の太十と昇之助の野崎とを聞く」とあり、下谷にあった寄席小屋に行って野沢吉花と豊竹昇之助の義太夫を鑑賞、1月4日には昇之助宛てのファンレターを書いて、投函していました。

志賀直哉
一人の芸人に深く思い入れするのは落語家に対しても同様のようで、東京帝国大学に入学した翌年の明治40年2月17日の日記には、「午后、常盤木倶楽部の研究会を聞く、馬楽痛快を極む」とあります。明治38年3月、日本橋の常盤木倶楽部で発足した落語研究会に志賀はしばしば足を運んでいて、三代目蝶花楼馬楽の芸に出会いました。注目されるのは、翌日2月18日に次のように書かれているものです。「朝高浜虚子の家へ行つて『坊ちやん』を買ひ正親町を誘ひ登校」「夏目さん休み、午后雪の中馬道八丁目の横丁を一つ一つ馬楽の家を探す、『坊ちやん』をヤルつもりだつたが遂に見当らず」。
夏目漱石の小説「坊っちやん」は前年の明治39年4月、雑誌「ホトヽギス」に一挙掲載されていて、その編集者、高浜虚子宅に立ち寄って志賀はそれを購入した模様です。それから同級生と大学へ行きましたが、当時講師をしていた漱石の講座は休み、午後になって志賀はなんと馬楽の自宅を探し回りました。それもどういう理由か、「坊っちやん」を馬楽に直接プレゼントしたかったからのようです。
同年3月2日、「木原店を通る、小さんの落語あり、一寸入つて、これを聞く、上手と感心した」などの記述もありますが、3月4日、5日と志賀は馬楽を追いかけます。4日、「夜、喜よしへ行つて「坊ちやん」を馬楽にやらうとしたが見損じてやる事が出来なかつた」。5日、「夜、喜よしへ行つて帰りに馬楽に「坊ちやん」をやる、大に喜むで居た、名前と番地も教へてやつた、来てもよいと云つてやつた」。無名大学生からの本の贈呈に喜んだ馬楽が、興奮した面持ちの志賀に対し名前と住所を尋ね、遊びに行ってもよいかと聞きただしているシーンが目に浮かびます。
この後も、志賀の寄席通いは続き、明治43年になると、常盤木倶楽部のほか神田の立花亭、京橋の金沢亭などにも足を運んでいます。10月1日、立花亭で「馬楽の顔を久しぶりで見る、鼻へ風がぬけて話しにくさうなのが、何んとなく惨然とした感じを与へた、梅毒からかも知れないが、それはシーリアスな感じを与へた。話は長屋の花見で中々上手だつた」。27歳になった志賀は、この年春に武者小路実篤、有島武郎らと同人雑誌「白樺」を創刊し、実質的に作家生活のスタートを切りました。
一方で馬楽は明治43年春に精神病で入院、退院後は胃がんを患って、大正3年1月、51歳の生涯を閉じました。最晩年の馬楽も志賀はずっとひいきにしていて、大正元年8月25日には立花亭に赴き、二人会を終えた馬楽に現金2円を手渡しています。
大正元年というと、志賀が唯一の長編小説「暗夜行路」を構想し、前身の「時任謙作」の執筆を始めた年でした。自伝色の濃い小説中に、こんな件があります。「一体、謙作は子供のうちから寄席とか芝居とか、そういう場所によく出入りした。それは祖父やお栄が行くのについて行ったので、然し後に中学を出る頃からは段々一人でもそういう場所へ行くようになった」。
志賀は代表作中にも、寄席に通っていた事実を記していました。