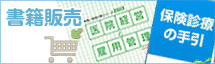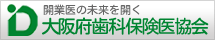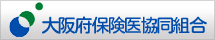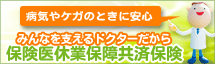宮本百合子
- 2020/8/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第25回 宮本百合子/恩田雅和
プロレタリア文学作家として日本の近代文学史上に名を刻む宮本百合子(1899~1951)は、大正末期から自身の結婚生活を描いた作品に取り組み、長編小説『伸子』にまとめました。
 東京生まれの百合子は高等女学校、日本女子大と進学しましたが、仕事の関係で渡米する父親に従い、大学を中退してニューヨークに渡りました。そこで古代の東洋語研究者の荒木茂と出会い、現地で結婚します。
東京生まれの百合子は高等女学校、日本女子大と進学しましたが、仕事の関係で渡米する父親に従い、大学を中退してニューヨークに渡りました。そこで古代の東洋語研究者の荒木茂と出会い、現地で結婚します。
『伸子』の主人公はもちろん百合子がモデルで、百合子の父は「佐々」、荒木は「佃」という名でそれぞれ登場し、ニューヨークでの父娘の暮らしぶり、伸子と佃が親密になる経緯などが詳しく語られます。アメリカに渡った1918(大正7)年、その時期のことで、小説中には見逃せない部分があります。
「ちょうどそのころ、ほとんど世界じゅうに瀰漫して悪性の感冒が流行していた。ニューヨーク市中で毎日おびただしい患者が脳や心臓を冒されて死亡した」。
20世紀最悪のパンデミックとされる100年前の「スペイン風邪」(1918~1920)が、当時アメリカ在住の百合子周辺にも襲っていたことが知られます。
「『感冒かなーとうとうとりつかれたかな』伸子は、心の中が冷えるように覚えた。彼女も父の声を寝室に聞いた瞬間それを思い、ぞっとしたのであった。秋から流行している悪性の感冒はまだ猖獗していた。」として、佐々が三十八度九分の高熱を発して入院する様子が書かれます。
この後、伸子も悪寒、全身の胴震い、痙攣などの症状を呈し、父親から感染してしまいますが、佃が切に伸子の病気を案じ、懸命に看病に尽くしました。「病院へ行った晩、佃は半ば夢中であった伸子に接吻した。伸子はそれを彼の情熱の告白と感じて応えた。彼にはもう再びそれから感情を元に戻すことが不可能であり、伸子にもできず、次第に離れ難く互いを思うようになって来た」。伸子と佃が一緒になったのは、パンデミックが奇貨とされたのでした。
百合子のニューヨークでのスペイン風邪罹患は、文学史で埋もれていた事柄と思われます。帰国後、離婚した百合子は、ロシア文学者の湯浅芳子との共同生活を送りつつ、荒木との結婚生活を振り返る小説を雑誌に少しずつ連載、昭和に入ってすぐ『伸子』のタイトルで著作を完成させました。
昭和6年日本共産党に入党、翌年党員で文芸評論家の宮本顕治と再婚し、中條から宮本に改姓して「宮本百合子」と名乗りました。
さて顕治が獄中にあった時に、百合子はいくつかのエッセイで落語に触れていました。「ラジオなどできく落語が、近頃は妙なものになって教訓落語だが、話の筋は結局ききてである働く人々の生活や文化の低さを莫迦らしく漫画化したようなものが多くていい心持ちはしない」(「〝健全性〟の難しさ」昭和15年12月15日都新聞)。戦時中ですから、落語はラジオを通し聞いていたようです。
「日本には『うどん屋』という落語がある。仕事の下手なものを云う表現に『うどんくい』というのがあると、新村出氏の辞苑に出ていた」(「うどんくい」昭和16年5月「オール女性」)とも記した文がありますので、百合子はどこかで落語の「うどん屋」も耳にしたことがあったのでしょう。
戦後発表された短編小説「菊人形」には、「おかずがあっても、おしまいの一膳はお茶づけにして、ほんとにサラサラと流しこむのだったが、おいしそうにひとしきりたべてさてお香のものへ移るというとき、おゆきはきまってリズミカルに動かしていたお箸を、そのリズムのまま軽く茶碗のふちへ当てて一つ小さく鳴らした」(昭和23年9月「大衆クラブ」)というシーンが出てきます。ここから嫁入り噺「たらちね」を作中で想起する百合子は、敗戦を経て出獄した顕治と12年ぶりの水入らず生活に入った喜びをかみしめているようでした。