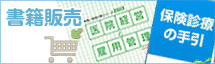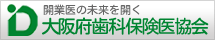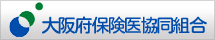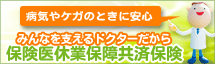徳田秋声
- 2020/5/25
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第22回 徳田秋声/恩田雅和
自然主義文学の完成者と評された徳田秋声(1871~1943)は、代表的小説のいくつかに寄席に出入りする市井の人たちを描いていました。
明治41年、当時の国民新聞に連載され、「人生の現實に目を向けた殆んど最初のもの」と自身で述べた『新所帯』には、新しく所帯を持つ新吉とお作の見合いの場に寄席を選ばせていました。「見合いは近間の寄席ですることにした。新吉はその友達と一緒に、和泉屋に連れられて、不断着のままでヒョコヒョコと出かけた。お作は薄ッぺらな小紋縮緬のような白ッぽい羽織のうえに、ショールを着て、叔父と田舎から出ている兄との真中に、少し顔を斜にして坐っていた」。そして二人はお互いの姿をチラチラと見やって、そのあと夫婦生活を始めます。
明治43年、読売新聞に連載の『足迹』は信州から上京した一家の娘お庄が奉公先を転々、嫁いだ先も飛び出すという波乱の続くストーリーです。その奉公先の「男は晩方になると近所の洗湯へ入って額や鼻頭を光らせて帰って来たが、夜は寄席入りしたり、公園の矢場へ入って、楊弓を引いたり」する遊び人です。
一方、苦しい生活を強いられている叔父のことも語られていて、「淋しくなると、叔父はよくお庄を引っ張り出して、銀座の通りへ散歩に出かけた。芝居や寄席のような、人の集まりのなかへも入って行ったが、傷を負ったようなその心は、何に触れても、深く物を考えさせられるようであった。お庄は高座の方へ引き牽けられている叔父の様子を眺めると、いたましいような気がしてならなかった」。寄席が登場人物の心理面を描写する手立ての一つに使われていました。
この後、明治44年、朝日新聞の『黴』、大正2年国民新聞の『爛』、大正4年読売新聞の『あらくれ』と連載された秋声の代表的長編小説のどれにも、わずかずつでも寄席が舞台の一つに取り入れられていました。
昭和10年から11年にかけ雑誌連載された『仮装人物』では、とりわけ重要な箇所で設定されています。秋声がモデルの50歳過ぎの小説家庸三が、近づいてきた20歳代の女弟子の葉子に振り回される話です。家に出入りしだした「葉子と散歩に出れば、きっと交叉点から左へ曲がって、本屋を軒並み覗いたり、またはずっと下までおりて、デパアトへ入るとか、広小路で景気の好い食料品店へ入ったりした。気が向くとたまには寄席へも入ってみた」と、寄席を二人の行き先の一つにしています。ですから、葉子が気ままに行方をくらますと、立ち回り先の一つとして「ある夜は寄席へ入って、油紙に火がついたように、べらべら喋る円蔵の八笑人や浮世床を聴いたものだった。そうしているうちに、彼は酷いアトニイに罹った」と、葉子を探し回るシーンがあります。葉子は「しゃべりだすと油紙に火がついたように、べらべらと止め度もなく田舎訛の能弁が薄い唇を衝いて迸しる」女なので、べらべら喋る円蔵に庸三は葉子を重ねて見ていたのでした。
ここで、四代目橘家円蔵や「八笑人」「浮世床」といった演目まで具体的に記されています。秋声の相当な落語好きの一面がうかがえるところですが、大正12年に雑誌「新演芸」に発表したエッセイがあります。「私が初めて東京へやつて来た時分には、寄席も随分盛つてゐたが、従つて、義太夫にしても落語にしても、巧い人が可なりゐたものだが、それも日露戦争までのこと」、「近頃は薩張り巧いのがゐない。先ず円右の巧さは小まちやくれた咄で、小さんは以前それほどでもなかつたが、近頃は非常に上手になつた。三語楼や馬生や、外にもまだ三四人相当に聴ける人もゐるにはゐるが、あとの連中は、ただ口真似で、何を喋つてるのか分らない」。
小説では円蔵の名しか出てきませんでしたが、秋声は寄席を通して何人もの名人に親しんでいました。