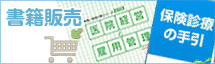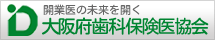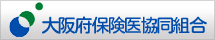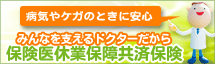林芙美子
- 2020/3/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第20回 林芙美子/恩田雅和
「私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない」で始まる『放浪記』の作者・林芙美子(1903~1951)は、さまざまな職業と男性遍歴を重ねて小説や詩に打ち込んだ人気作家でした。
 現在の北九州市門司区に生まれ(『放浪記』では山口県下関市出生)、行商の母と義父とともに下関、直方、長崎、佐世保など放浪に近い形で転々としました。11歳の頃、芙美子は広島県尾道市に落ち着き、地元の小学校と高等女学校を卒業。その後、因島出身の東京の大学生を頼って上京し、女中、下足番、女工、女給など種々の職業に携わりました。
現在の北九州市門司区に生まれ(『放浪記』では山口県下関市出生)、行商の母と義父とともに下関、直方、長崎、佐世保など放浪に近い形で転々としました。11歳の頃、芙美子は広島県尾道市に落ち着き、地元の小学校と高等女学校を卒業。その後、因島出身の東京の大学生を頼って上京し、女中、下足番、女工、女給など種々の職業に携わりました。
その大学生に婚約を取り消された後、詩人の新劇俳優と同居、その縁で萩原恭次郎、辻潤、野村吉哉、壷井繁治らダダイズム系の詩人たちを知りました。新劇俳優と別れてからは、その一人野村と一時同棲生活も送りました。
大正末年のその頃、すでに文壇で地位を築いていた徳田秋声のもとに芙美子は通い始めます。昭和10年に発表された「文学的自叙伝」によると、「私はひとりになると、よく徳田先生のお家へ行ったし、先生は、御飯を御馳走して下すったり落語をききに連れて行って下すったりしました」。
当時秋声宅には女弟子の山田順子が出入りしていて、秋声は芙美子を交えた3人で出かけたこともあったようです。そのあたり、『放浪記』第二部に記されています。「『ね、先生! おしるこでも食べましょうよ。』順子さんが夜会巻き風な髪に手をかざして、秋声氏の細い肩に凭れて歩いている。」「しる粉屋を出ると、青年と別れて私達三人は、小石川の紅梅亭と云う寄席に行った。賀々寿々の新内と、三好の酔っぱらいに一寸涙ぐましくなっていい気持ちであった」。このように、秋声に寄席に誘われた記憶は芙美子には大きいものでした。
ここで言われている「三好の酔っぱらい」とは、昭和の初めまで音曲師として活動していた二代目柳家三好による酒にまつわる噺か唄に、芙美子は感心していた様子がうかがえます。
『放浪記』第三部には、別れた男に宛てた手紙文が詩のように書かれた一節があります。「インキを買って帰る。/何とかしておめもじいたしたく候。/お金がほしく候。/ただの十円でもよろしく候。/マノンレスコオと、浴衣と、下駄と買いたく候。/シナそばが一杯たべたく候。/雷門助六をききに行きたく候。/朝鮮でも満洲へでも働きに行きたく候。/たった一度おめもじいたしたく候。/ 本当にお金がほしく候。」
雷門助六の名が突然に出てきますが、この後、「夜、上野の鈴本へ英子さんと行く。猫八の物真似、雷門助六のじげむの話面白し。ああすまじきものは宮づかえ」という記述があり、勤めの同僚と定席の鈴本演芸場に足を運んで、助六の噺を好んでいたことが分かります。この助六は、40年間高座を勤めた昭和8年に引退興行を催した六代目で、華麗な踊りと手堅い語り口で平成の初年まで多くのファンを引き付けた八代目の実父にあたります。この時の六代目は、生まれた子供に長い名前をつけて戸惑う「寿限無」を演じて、芙美子らを楽しませたようです。
『放浪記』は、芙美子が書き溜めていた日記風の雑記帳をもとに、昭和3年、雑誌「女人芸術」に連載されて注目され、昭和5年単行本化されました。たちまちにベストセラーとなり、第二部の『続放浪記』が刊行され、戦後には第三部も出版されました。
一躍、人気女流作家となった芙美子は、戦時中、報道班員としてジャワ、ボルネオなど南方に従軍、戦後は「晩菊」「浮雲」など荒涼とした人生後半の哀しみをじっくり描く名作を残し、わずか47歳の生涯を閉じました。