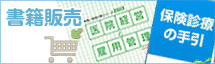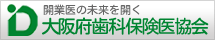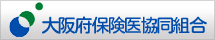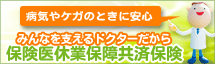吉行淳之介
- 2020/1/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第18回 吉行淳之介/恩田雅和
戦後まもなくに「第三の新人」として文壇デビューした吉行淳之介(1924~1994)は、性の問題を突き詰めた問題作をいくつも発表しました。
 娼婦に引かれながら大学教授の娘の心をもてあそぶ男の「原色の街」(昭和27年)、素人風な娼婦が馴染みの男に操をささげる「驟雨」(昭和29年)、心の傷をいやしに娼婦のもとに通う男の「娼婦の部屋」(昭和33年)など、この頃の吉行は、娼婦の街に足を踏み入れつつサラリーマン生活を送る男たちを一貫して書いていました。
娼婦に引かれながら大学教授の娘の心をもてあそぶ男の「原色の街」(昭和27年)、素人風な娼婦が馴染みの男に操をささげる「驟雨」(昭和29年)、心の傷をいやしに娼婦のもとに通う男の「娼婦の部屋」(昭和33年)など、この頃の吉行は、娼婦の街に足を踏み入れつつサラリーマン生活を送る男たちを一貫して書いていました。
この時の「驟雨」によって吉行は芥川賞を受けましたが、左肺に空洞が見つかったため前年より出版社を退職、千葉県佐原で3カ月療養の後に東京の清瀬病院に転院していて、受賞式には出席できませんでした。
入院時の体験が元になったとみられる短編小説「漂う部屋」(昭和30年)に、こんな一節があります。
「私はこの部屋で迎えた初めての夜を忘れることができない。私は仰臥して天井を見詰めていた。」「不意に、隣のベッドから忍び笑いの声が洩れてきた。」「また笑い声、今度は少し大きな笑い声だ。隣のベッドからばかりではない、暗い病室のあちこちから笑い声が起りはじめた。」大部分の同室者が皆レシーバーをあててラジオの落語番組を聞いていたからで、「間もなく私も片耳レシーバーを購って、『部屋のラジオ』の聴取者の仲間入りをし」、同室者がどう聴き取っているのか、聞き耳をたてました。
「古典落語と新作落語にたいしての反応の具合とか、いわゆるクスグリに類する笑わせ方にたいする反応とか、私にとってこの小規模の実験はなかなか面白いものだった。」というのですから、消灯後、入院患者が一斉に落語に耳を傾ける大部屋の様子は狭い空間での落語会の様相を呈しているようでした。
昭和48年から49年にかけて吉行は、「すすめすすめ勝手にすすめ」と題した軽妙なエッセイを新聞連載しました(後に『贋食物誌』と改題され単行本化)。そこでは、「私は東京育ちで、子供のころからよく寄席に連れて行かれた。ずいぶん以前になくなったが、神楽坂の上に寄席があった。」などと、寄席の思い出を語っています。
そこでは、週刊誌対談した三遊亭円生、柳家三亀松といった名人上手についても記されていますが、実際に聞いた落語家を述べた箇所もありました。「子供のときの記憶なのだが、ふしぎなものでそのときの人の名まで覚えていて、これが柳亭左楽である。その道に精しい人にたずねてみると、芸はたいしたことはないが当時の落語界のボス的存在だったという。私が一番好きだったのは、志ん生である。破格というかアブストラクト風といおうか、そのくせ噺のつづいてゆく糸は切れないところがまことによかった。」として、志ん生演ずる「寝床」の「その間の良さに、爆笑しながら感服した。」と言っています。
このように、吉行には落語をよく聞き込んでいた一面がありました。昭和55年映画化されて「夕暮れ族」という流行語まで生んだ長編小説『夕暮れまで』は、中年男と愛人の若い女が性行為をしているのかいないのか、謎のままに終わっています。第一章に「男は、傍の女の気配を窺っている。『そのときの顔って、こんな具合だったでしょう』と、女が言って、掌を離す。」というくだりがあって、男は有名な怪談を想起します。ラフカディオ・ハーンが著した『怪談』の一つ、「のっぺらぼう」のことでした。
実は、これと同じ内容の噺が落語にもあります。5年ほど前、東京の立川談四楼が繁昌亭昼席に出演した際にかけたのが、「こんな顔」とタイトルされた演目でした。東京では今も流通しているネタのようでして、吉行もずっと昔に実際に聞いていた可能性を捨てきれません。