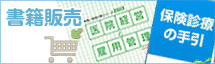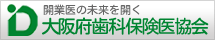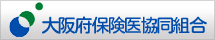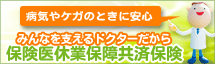田辺聖子
- 2019/9/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第14回 田辺 聖子/恩田雅和
今年6月、91歳の長寿を全うした田辺聖子は、落語台本作家としての一面を持ち合わせていました。
 「実をいうと私は、私の書く短篇のあるものを落語小説とひそかに呼び、これを大阪弁で咄してもらうことを夢みている」(『ほととぎすを待ちながら 好きな本とのめぐりあい』1992年10月中央公論社)と述べ、「勉強が大きらいで、やすみ時間に、落語やピンク小咄をしゃべるのが好き」(『イブのおくれ毛Ⅱ』1978年5月文春文庫)とも、学校の生徒に自身をなぞらえたエッセイで語っています。
「実をいうと私は、私の書く短篇のあるものを落語小説とひそかに呼び、これを大阪弁で咄してもらうことを夢みている」(『ほととぎすを待ちながら 好きな本とのめぐりあい』1992年10月中央公論社)と述べ、「勉強が大きらいで、やすみ時間に、落語やピンク小咄をしゃべるのが好き」(『イブのおくれ毛Ⅱ』1978年5月文春文庫)とも、学校の生徒に自身をなぞらえたエッセイで語っています。
よく知られているように田辺聖子は、やわらかい大阪弁を駆使した「カモカのおっちゃん」シリーズ、「源氏物語」などの古典を翻案した小説、また川柳作家や女流作家の評伝など残しました。書くスタイルをさまざまに模索した結果、それらが世代を超えて愛される作品となりました。
そのスタイルをあれこれ考えていた時期に、田辺聖子は落語との大きな出会いがあったようです。「落語を聴いていると、じつにさまざまなヒントを与えられる。人物描写の溌剌たるクロッキーがそこにある。躍動する会話がある。」「(いやいや、ははあ、こういうところに、描写のコツが秘匿されてるんだなあ)と思ったりする。『読む落語』をめざしている私としては、まことによく『お勉強』でき、楽しめるのである。」(『楽老抄 ゆめのしずく』1999年2月集英社)思いのほか、田辺聖子は落語の影響を受けていて、彼女の発表する小説は活字で楽しむ落語を目標にしていたことがうかがえる一文です。
当然のこと落語家にも深い関心を抱いていて、中でも六代目笑福亭松鶴についての思い出の文章がありました。「私はいつか、大一座の中で師匠によそながらお目にかかったことがあった。そのとき師匠は大一座をずーっと見渡し、私の所へ視線がいくと、(ハテ見なれぬオナゴがいよる)という風情で、じっと私を見つめられる。その視線というのが、じつに色けがあって、別の好奇心むき出し、値踏みするようにためつすがめつ、イキイキと面白がっていて、躍動する若々しい好奇心を感じさせられた。私は一ぺんに師匠を尊敬し好きになってしまった。」(『イブのおくれ毛Ⅰ』1978年3月文春文庫)
そんな田辺聖子が満を持して、落語台本のつもりで書いた小説があります。1974年筑摩書房から刊行された『おせいさんの落語』で、雑誌連載された「貸ホーム屋」「愛のロボット」などの短編小説11編が収められています。
ほとんどが現代に設定され、発表された当時の世相が描かれたものもあり、「ツチノコ女房」は全国各地で捕獲騒ぎのあった未確認動物がテーマにされています。幻のツチノコを探しているうちに、逆に人がツチノコに捕まってしまいます。「人間がツチノコつかまえる、いうのは分るで。しかしツチノコが人間つかまえて、どないしょう、いうねん」「賞金もろうて、みせもんにして国中まわって左ウチワでくらすか。メスと一しょにツガイでつかまえてふやしたら、食いっぱぐれないというもんや」と、ツチノコ同士のやりとり。一つ目小僧を探して見世物にしようと企み、一眼国に紛れ込んで捕まり、見世物に出されるという古典落語「一眼国」のパロディでした。
また「すずめ女房」は助けられた雀がおっちゃんに恩返しをする話ですが、狸がお礼にサイコロになって言われた通りの賽の目を出す落語「狸賽」と一部そっくりです。
たくさんの落語の演目を聞きこんで田辺聖子文学の薬籠中のものにしたことが、これら落語台本の小説の裏付けになっていたことは確かです