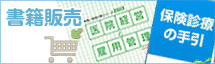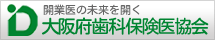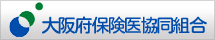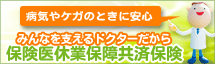田村 隆一
- 2019/8/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第13回 田村 隆一/恩田雅和
終戦後まもなく月刊詩誌「荒地」の創設に参加した田村隆一(’23~’98)は、戦後最大の詩人の一人といわれています。
 昭和31年刊行の田村の処女詩集『四千の日と夜』に収められた「十月の詩」には、終戦直後の秋、殊に十月の心象風景が印象深く記されています。一部を引用しますと、「十月はわたしの帝国だ/わたしのやさしい手は失われるものを支配する/わたしのちいさな瞳は消えさるものを監視する/ わたしのやわらかい耳は死にゆくものの沈黙を聴く」とあります。
昭和31年刊行の田村の処女詩集『四千の日と夜』に収められた「十月の詩」には、終戦直後の秋、殊に十月の心象風景が印象深く記されています。一部を引用しますと、「十月はわたしの帝国だ/わたしのやさしい手は失われるものを支配する/わたしのちいさな瞳は消えさるものを監視する/ わたしのやわらかい耳は死にゆくものの沈黙を聴く」とあります。
のちにこの詩について田村は、「敗戦、占領、そして朝鮮戦争と、(昭和二十年代の)十月は、地も空も不安定だ。死も生も、ともどもに揺れうごいて、焦点はさだまらない。それでぼくは、固い詩型の中に、『十月』をとじこめようとしたのかもしれない」と註しています。
不安定で焦点の定まらない日々は、この時期の十月のみならず、昭和17~18年、田村が二十歳を迎えようとした頃も同じだったようです。昭和56 年から7年近くにわたって雑誌連載された自伝的エッセイ『ぼくのピクニック』に、その辺の事情が回想されています。「寄席へ行っても、映画館へ行っても軍事色一点張りだったから鼻白むばかり」「ぼくは、自分自身が兵隊にかり出される悪夢にばかりおびやかされていたから、江戸化政期の読み物をあさったり、古典落語に熱中したりして、自分をだます工夫ばかりをしていた」。
そんな時に、神田錦町で七代目三笑亭可楽(昭和19年没)の会が、また上野で八代目桂文楽(昭和46年没)の会が、それぞれ毎月1回ずつ開かれていることを聞きつけ、田村はそこに足を運びます。「可楽は噺を二つ。まず前座噺からはじまるのだが、この名人の手にかかると、どんな前座噺でも、たちまち古典の名作中の名作になるのだから、不思議というほかはない。たとえば、『竜田川』を目で見、耳で聞いているうちに、化政期の吉原の夜景が、すごいリアリティとなって、ぼくの心を開くのである」
また文楽は、「後進を育てるために、かならず一人、前座をつとめさせた。なかでも、ぼくが舌を巻いたのは、『小きん』という前座で、この人が、いまの『小さん』である。むろん、文楽は十八番を、毎会、一つ一つ披露してくれた。当時の寄席ではタブーになっていた『明烏』から一八ものと呼ばれている、『うなぎの幇間』など」と、思い出を語っています。
のち落語界初の人間国宝となる五代目柳家小さん(平成14年没) の小きん時代の一面が見て取れる一方、廓噺や艶笑噺などを自粛していた戦時中の一時期に文楽は平気でそれらを演じていた様子がうかがえます。
昭和20年1月海軍少尉の田村は、最後の休暇を過ごそうと任地先の滋賀海軍航空隊から東京・大塚の生家に向かいました。近くにある寄席の鈴本のトリが文楽だったので、田村はそのまま楽屋へ行きます。
「楽屋の入口で、文楽師匠に面会を申しこむと、都家かつ江さんがギョッとした顔で、ぼくの顔を見上げたのを、いまでも忘れられない。やがて師匠がニコニコした顔で奥から出てくると、ちょうど噺が終ったところだと仰言る。『よろしかったら、家で一献さしあげたいと存じますが、ご都合いかがでしょう』と、ぼく。『ようがす、お伺いしましょう』まさか一年ぶりで帰宅する息子が、噺家と連れだってやってくるとは、父母も夢にも思っていなかったから、都家かつ江さんみたいにギョッとした顔をした」。
軍服を着た見も知らない青年の誘いを受けて酒を飲む文楽も、その芸に引かれていた田村自身も、戦争に対し彼らなりの反抗を示していたエピソードでした。