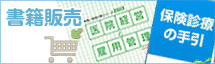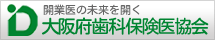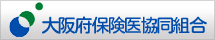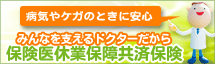小松左京(前編)
- 2020/6/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第23回 小松左京(前編)/恩田雅和
1964年8月、日本SFシリーズの先陣を切って早川書房から刊行された小松左京(1931~2011)の長編小説『復活の日』の第1部に、次のような一節があります。
 「ほとんど毎年大小の規模でくりかえされている各種のタイプのインフルエンザに対し、これはまったく新しい型の――人類のほとんどが免疫性をもっていない新種のウイルスという事だ。『新型インフルエンザ発生す!』の新聞見出しを読んだ人々の胸には、今世紀における、二つの大流行の不安な記憶がうかんで来た」。
「ほとんど毎年大小の規模でくりかえされている各種のタイプのインフルエンザに対し、これはまったく新しい型の――人類のほとんどが免疫性をもっていない新種のウイルスという事だ。『新型インフルエンザ発生す!』の新聞見出しを読んだ人々の胸には、今世紀における、二つの大流行の不安な記憶がうかんで来た」。
半世紀以上前、当時まだ30代前半の小松の書き下ろし小説に、現在の日本の状況を予知するような文章があるのには驚かされます。この二つの大流行とは、「第一次世界大戦終了の年、すなわち一九一八年に発生し、全世界を荒れまくった、いわゆる〝スペインかぜ〟、もう一つは記憶もあたらしい一九五七年から翌年へかけて、世界一周したA2型ウイルスによる〝アジアかぜ〟」と、パンデミー(パンデミック)という言葉まで使われて紹介されています。
この新種ウイルスの都市部での罹患率は70パーセントで、患者は3千万人に達し、全国での死者は1千万を超えそうという悲惨さです。大東京も、小説の冒頭では廃墟のような描かれ方がされています。世界的に新種ウイルスが蔓延する中で、各国が派遣していた学術観測隊のいる南極基地のみがウイルスに感染せずに、約1万人の隊員が生き延びます。そしてそのうちの何人かが生存し続け、人類復活の日を目指すというエンディングでした。
1974年『日本沈没』、1985年に『首都消失』と、小松は壮大なSF長編小説を発表し、いずれも日本の国に危うい一面があることに警鐘を鳴らしていましたが、長編第1作には、細菌によって危機に直面する人類全体がすでに書かれていました。しかもこの『復活の日』が出版されたのは、東京オリンピックが開催されるわずか2か月前のことで、東京オリンピック・パラリンピック2020が来年に延期されたことと妙に因縁めくと思うのは私だけでしょうか。
年譜によりますと小松は、大阪市西区に生まれ、幼くして兵庫県西宮市に転居、神戸一中、旧制三高を経て京都大学文学部でイタリア文学を専攻しました。1969年に受験雑誌「蛍雪時代」に連載された小松のエッセイ「やぶれかぶれ青春記」には、「私は、三高時代を、自分の人生で一番すばらしかった一年であると、はっきりいうことができる。」と三高の学生時を振り返っています。京都の街中に下宿して、多くの友人たちに押しかけられ、遅くまで酒を飲んで酔っぱらったことや花札をしたこと、またアルバイトに精を出したことなどが回想されています。さらに、当時京都市中にあった寄席に出会ったことにも触れられていました。
「京極の中の『富貴亭』という寄席へ行くことをおぼえると、私のバイト料はほとんど寄席の入場料に化けた。いれかえなしの三時間半、わりと大看板が来て、特に神田伯龍の、すごいばかりの色っぽさに、私は夢中になり、とうとう東京まで、普通列車で出かけて聞きにいった。三笑亭可楽、松葉家奴、声色の悠玄亭玉介、松旭斎天一、今でも元気な、そして当時はもっと元気だった、桂南天老も、たしか見たように思う」。
その頃吉本興業に所属し、玄人筋に好まれていた講談の五代目神田伯龍ファンであり、若き日の桂米朝が私淑していた桂南天の高座まで見ていた小松は、寄席通の少年でした。終戦後間もない京都の定席は、入れ替えなしの長時間公演であったこともここから分かります。
(後編に続きます)