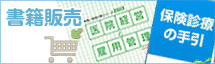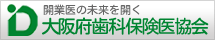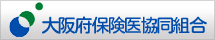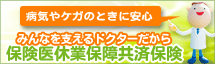周 作人
- 2019/10/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第15回 周 作人/恩田雅和
中国の文豪・魯迅の実弟で散文作家の周作人(1885~1967)は、日本に深く関わり、兄の文学を現代日本に紹介した日本文化研究者でもありました。
 周作人は魯迅が仙台医専を中退して東京に移るとほぼ同時に、日本に留学し、本郷でしばらく兄弟同居しました。「私どもの住んでいたのはありきたりの下宿屋で四畳半の一間に、本箱とあとは机が一つに座蒲団二枚があるきり」(「留学の思い出」)の暮らしでした。
周作人は魯迅が仙台医専を中退して東京に移るとほぼ同時に、日本に留学し、本郷でしばらく兄弟同居しました。「私どもの住んでいたのはありきたりの下宿屋で四畳半の一間に、本箱とあとは机が一つに座蒲団二枚があるきり」(「留学の思い出」)の暮らしでした。
1921年から1922年、魯迅は代表作『阿Q正伝』を発表しますが、夏目漱石の『吾輩は猫である』に影響されていたと、同居していた弟に回想されます。「それが活字になるごとにすぐに続けて買って読み、また『朝日新聞』に連載されていた『虞美人草』を毎日熱心に読んでいた。」「後日書いた小説は漱石の作風に似てはいないけれども、その嘲諷中の軽妙な筆致は実は漱石の影響を相当強く受けたもの」(「魯迅について その二」)ということでした。
魯迅は1909年夏、7年に及ぶ留学生活を切り上げ帰国しましたが、周作人は日本に残り、法政大学予科、立教大学商科と学び、賄い婦だった羽太信子と結婚します。「私は東京に続けて六年暮したにすぎない。しかしそこは私の気に入り、第二の故郷の感を抱かせた」(「東京を懐う」)と言う周作人は、「戯作文学、俗曲、浮世絵、陶銅漆器、四畳半の書斎、小袖に駒下駄」が好きだったと、留学生活を振り返っています(「日本浪人と『順天時報』」)。
こうした東京の庶民暮らしを身近にしたのも日本人妻が傍にいたからで、周作人の関心は書き言葉ではなく、やがて話し言葉に向かいました。「学ぶのは、書面の日
本語ではなく、実社会で使う言葉だった。出来れば現代小説や戯曲を読みたいところだが、作品が多すぎて、どこから手をつけて良いか分からず、滑稽味のあるものだけを選んで読むことにした。それは文学では「狂言」と「滑稽本」で、韻文では川柳という短詩だった。」「このほかにも一種の笑い話があり、「落語」と呼び、最後にオチ(原語では着落)があり、それは笑うところである」(「日本語を学(続)」)。
主として耳で聞く落語にも興味を持った周作人は、妻と住んでいた本郷西片町を拠点に、「鈴本亭はその通りの果てにあり、私達がしょっちゅう通った寄席だった」(小川利康訳『知堂回想録』)と、上野にある定席に夫婦揃って足を運んでいたことを語っています。そして実際に落語を聞いた感想も述べていました。「かつて柳家小さが高座に上るのを見たが、あたかも田舎の寺子屋の師匠がポツリポツリと『論語』など講じている趣きだった。それでいながら聴衆は笑いをこらえきれなくなるので、ことさら泣き笑い、歌い酔うまでもないようだった。それにつけても不審でならぬが、中国にはどうしてこういうものがないのだろうか。我々は真面目くさった説書〔講釈〕かふざけた相声〔万歳〕しか知らないのである。説笑話もないではないが、単に個人同士のなぐさみごとにすぎず、雑芸場裡にこの技を売る者のあるを聞かぬ」(「日本の落語」)。三代目柳家小さんの芸に触れた思い出をもとに、日本の落語のような芸能がなく、中国では「絶えてしまった」のかと案じる1936年の文でした。
後に周作人は北京大学教授に就任し、日本文学専攻コースを設置するなど、日本文化と文学の紹介に尽力。それが日本の敗戦後、対日協力者の一人として北京で拘束され、戦後は変則的な蟄居生活を余儀なくされました。そんな不遇な晩年でも、『周作人・松枝茂夫往復書簡集 戦後篇』を見ますと、1956年4月、日本の中国文学者に三遊亭円朝作『牡丹灯籠』を送るよう依頼状を書くなど、落語への関心は持ち続けていました。
※訳文は松枝茂夫、木山英雄両氏によりました