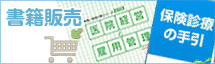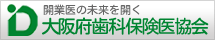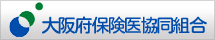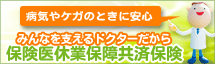泉鏡花
- 2019/5/15
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第10回 泉鏡花/恩田雅和
「高野聖」をはじめ幻想文学ジャンルに名を残す一方、「婦系図」など新派劇に原作を多く提供した泉鏡花(1873~1939)は、明治から昭和の初期まで幅広く読者に親しまれました。
 その鏡花はデビューまもない明治27年からの3年間であわせて5つの作品に、畠芋之助という滑稽なペンネームで発表していました。その一つ、子ども向けの雑誌『幼年玉手箱』に書かれた「鬼の角」は、鬼が人間界に金色の角を落として霊力を失い、拾った者が異常な力が働いて人格が変わるという、鬼と人との逆転現象の面白さを描いていました。この中に、食いしん坊の商家の小僧がお汁粉を楽しみとして、「一番好いものが真打といふので、先づ前座の塩煎餅一銭が取着で」と話すくだりがあり、真打、前座の寄席用語が使用されています。ペンネーム、内容からいって、この小説を鏡花は、落語を意識して書いたものと考えられます。
その鏡花はデビューまもない明治27年からの3年間であわせて5つの作品に、畠芋之助という滑稽なペンネームで発表していました。その一つ、子ども向けの雑誌『幼年玉手箱』に書かれた「鬼の角」は、鬼が人間界に金色の角を落として霊力を失い、拾った者が異常な力が働いて人格が変わるという、鬼と人との逆転現象の面白さを描いていました。この中に、食いしん坊の商家の小僧がお汁粉を楽しみとして、「一番好いものが真打といふので、先づ前座の塩煎餅一銭が取着で」と話すくだりがあり、真打、前座の寄席用語が使用されています。ペンネーム、内容からいって、この小説を鏡花は、落語を意識して書いたものと考えられます。
明治30年以降、畠芋之助は使われておらず、明治32、33年の2作品に白水楼主人のペンネームが見えるだけで、あとは一貫して泉鏡花の名前で作品は発表され続けました。
そんな中、明治32年、長編小説『湯島詣』が単行本で出版されました。苦学して大学を卒業、子爵家に婿入りした神月梓が、湯島天神下に住む芸者蝶吉とひょんなことから懇ろになる話です。梓は2歳上の妻龍子と蝶吉との板挟みに遭い、悲劇的な結末を迎えてしまいますが、生前の蝶吉ファンの一人として落語家が登場しています。「三遊派の落語家に圓輔とて、都合に依れば座敷で真を切り、都合に因れば寄席で真を打つ好男子」と、老舗の寄席鈴本などに出入りしながら、ひいき筋から座敷がかかれば座も持つ真打と書かれています。
当代の三遊亭圓輔は三代目で、初代は三代目三遊亭圓生没後の明治中頃に四代目圓生門に移って百生と改名し、後に幇間に転向したようです。二代目は同じく明治半ば京都に移住して桂藤龍を名乗り、新京極の寄席に出演していたとのことで、いずれにしろ『湯島詣』が刊行された頃、圓輔は実在していました。鏡花の頭には、初代か二代目かどちらかの圓輔のイメージがあって、小説中に登場させていたのでしょう。
ちなみに「婦系図」は明治40年、『やまと新聞』に連載され、翌年新派で舞台化、のち映画やテレビドラマにもなって、鏡花の代表作の一つになります。主人公二人の出会いの場が湯島天神の境内であったことから、ドラマでは「湯島の白梅」のタイトルでも知られるようになりましたが、『湯島詣』はその先駆け作品であったといえます。
明治43年、今度は寄席を舞台にした長編小説『三味線堀』を鏡花は「三田文学」に発表しました。寄席の名は、浅草小島町の場末「古くからあるが、餘り人の知らぬ」新瀧です。この新瀧の出演者は、「個より浪花節さへ、潜りの真打。田舎廻りの芸人徒合」が多く、「落語家とても右同断、自分達が高座で饒舌る、弟子の又弟子の其弟子」というのですから、素人か入門まなしの若手しか出ていない寄席です。そこに下足番と席亭が一計を案じて清元の美人芸人、雪江に出演交渉し、出かけることになったその初日、赤猫が突然現れて雪江を気絶させ邪魔をするという、鏡花らしい超自然的な筋運びの作品です。
明治37年5月の万朝報によりますと、その頃の東京市中には110の寄席がありました。しかし浅草には新瀧という寄席小屋は見当たらず、どうやら架空の場所を舞台にしたようでしたが、これらの作品によって鏡花文学の中には落語家も寄席もしっかりと書き込まれていました。