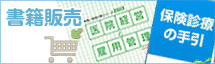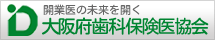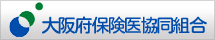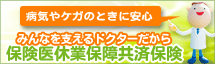夏目漱石
- 2018/8/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第1回 夏目漱石/恩田雅和
天満天神繁昌亭支配人の恩田雅和氏が「作家」と「寄席」の意外な接点にスポットを当てる新連載が今号からスタートします。
夏目漱石が落語好きで、寄席によく出入りしていたことがうかがえる本人の回想文がいくつかあります。作家専業になる直前、明治40年の雑誌「趣味」で、「僕の昔」という談話を載せています。
落語はすきで、よく牛込の肴町の和良店へ聞きにでかけたもんだ。僕はどちらかといへば小供の時分には講釈がすきで、東京中の講釈の寄席は大抵聞きに廻った。何分兄等が揃って遊び好きだから、自然と僕も落語や講釈なんぞが好きになって仕舞ったのだ。
このように、和良店(わらだな)という寄席のほか東京中の寄席は聞いて回った、と漱石自身語っていました。
死去の前年に書かれたエッセー「硝子戸の中」では、子供の頃の住まい近くに豆腐屋があったことを思い出し、「この豆腐屋の隣に寄席が一軒」あり、「よく母から小遣を貰って其所へ講釈を聞きに出掛けた」として、ごく近所の寄席にも親しんでいたことも述べています。
豆腐屋といえば、「僕の昔」の前年に発表された小説「二百十日」では登場人物の職業にもなっているものです。そもそも「二百十日」は、豆腐屋の子供の圭さんと友人の碌さんの二人の会話体だけでストーリーがほぼ進行するという、漱石の小説では唯一といっていいくらいにユニークな作品です。もっと言えば、落語の台本として実験的に試みた文体であったとも考えられ、この時の漱石の意識では豆腐屋と寄席とが密接であったことが想像されます。
そうでありながら、二人の主人公の会話は次第に過激になり、世の中が不公平だから華族や金持ちを豆腐屋にしようと言い出して、碌さんも豆腐屋になろうかとあいづちを打つくだりも出てきます。
「これから追い追い華族や金持ちを豆腐屋にするんだからな。滅多に困っちゃ仕方がない」「すると僕なんぞも、今に、とおふい、油揚、がんもどきと怒鳴って、あるかなくっちゃならないかね」「華族でもない癖に」「まだ華族にはならないが、金は大分あるよ」「あってもその位じゃ駄目だ」「この位じゃ豆腐いと云う資格はないのかな」
さて、ここに唐突に「とおふい、油揚、がんもどき」あるいは「豆腐い」というセリフが出てきますが、実はそれがそのままオチになった落語があります。江戸落語の「甲府い」がそれで、あらすじを紹介しますと、甲府から江戸に出て来た善吉がひょんなことから豆腐屋で働くことになり、「豆腐い胡麻入がんもどき」と声を出しながら懸命に売り歩きます。そしてしまいに店の一人娘お孝の婿養子に出世、夫婦で甲府に錦を飾るという内容です。
「二百十日」発表の6年前、明治33年10月雑誌「百花園」に掲載された六代目桂文治によるこのネタの速記が残されていましたので、ちょっと見てみましょう。
「ヲーイ豆腐やの若旦那、どちらへ御出なさるんでございます」善吉がふりむいて「甲府ィー(豆腐ィ)」お孝が「お参り願ほどき(胡麻入がんもどき)」
これが「甲府い」のエンディングで、明らかに漱石はこの落語を小説中に取り込んでいたことがうかがえます。江戸落語の「熊さん」「八さん」という主要人物二人をあげるまでもなく、圭さん碌さんは落語の主人公になぞらえられていて、漱石の落語好きがここにも反映されていたことが理解されます。