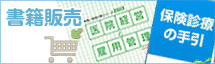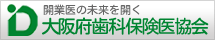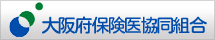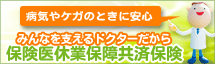- Home
- 「都構想」!?どこがウソ!?市解体の実態を探る
- 〈第15回〉コロナ禍で改めて問われる大阪の街の在り方
〈第15回〉コロナ禍で改めて問われる大阪の街の在り方
- 2020/7/25
- 「都構想」!?どこがウソ!?市解体の実態を探る
編集者/著述家 江 弘毅
7月初旬のとある新聞に心斎橋北商店街理事長のインタビューが載っていた。中国人向けのドラッグストアや眼鏡店が5店舗閉鎖し、4店舗が休業中であるとのことだ。飲食店の店主は7月になっても「夜8時以降はお客が来ず、2回転しない」と嘆いている。
少なくとも半年前までは外国人客でいっぱいで、難波、心斎橋の夜の御堂筋線と街は日本人がアウェーの状態だった。新型コロナウイルス禍でそんな景色が一転した。
理事長は、2010年あたりから訪日客が押し寄せ、商店主は家賃高騰で全国資本のチェーン店に店を貸し出し、古い店が姿を消したと指摘する。そんなところに今回のコロナ禍が容赦なく襲った。根本的に以後の街づくりについて考えなくてはならない。理事長は「ミナミ本来の街に立ち返ること。それは庶民的でうまくて安い街です」と言って、インタビューを結んでいる。
わたしは80年代から大阪と差し向かいで都市型雑誌の編集をやってきて、大阪の街の魅力や動きを取材してきた。その大きな特徴は、1970年代のアメリカ村も90年代の南船場もその次の堀江も、誰かが何かをやろうとして店をつくり、そこから自然発生的に店が集まって人を呼び、その点が線になりエリアになっていったことだ。今なら中崎町あたりもそうだ。
店同士そして客は顔と顔の関係性でつながっていて、アーバン・ビレッジと呼ぶにふさわしい仲間意識と時代感覚を時間をかけて熟成してきた。そこは単なる消費空間ではなく、厚みのある生活空間であり、それをわれわれは「街的」と表現していた。
何から何まで経済軸で企画され、客をターゲットとして位置づけてマーケティングで数字を弾く大規模商業施設とテナントの都市空間ではない。すなわち行政による再開発や電鉄のターミナル開発、大手総合不動産会社のプロジェクトによる「資本の街づくり」とは違った、大阪的なコミュニケーションの空気感が漂った〝リアルな街〟なのだ。
ミナミの場合は、アメリカ村の北隣の南船場と西の堀江は成り立ちも手触りも全然違った街が重層的に重なっている。環状線の駅でいえば、天満と福島は大阪駅からどちらも一つ目だが、まったく違った性格の街が広がっている。そこが多様性にあふれたスーパーシティの大阪の街的な魅力である。
その街的視座から都構想を見ると、大阪市を解体して4つの特別区を設置、大阪府(これが都だといわれている)の権限下に置くという一極集中型行政に他ならない。万博やIR・カジノといった「のっぺりした大規模開発型」は、先の心斎橋北商店街の理事長の「本来の街に立ち返る姿勢」とは真逆の方向になる。
コロナ社会の下、われわれは必然的に新しい「居場所」を街場に求めることになる。それは花火を上げることでも、賭博を公認することでもないのが明らかだ。
次号から筆者を交替します