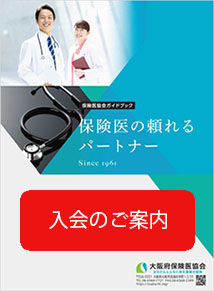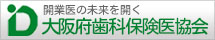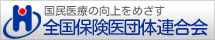大阪府保険医協会は、病床削減に関する自公維3党合意に対し下記の談話を発表しました。
報道関係各社 御中
自民党、公明党、日本維新の会は、6月6日に病院のベッドを約11万床削減する方針で合意した。「骨太の方針2025」に反映させる方向で、医療費約1兆円の削減を見込んでいる。日本維新の会は、厚労省が実施している、病床を減らす病院に給付金を支給する「病床数適正化支援事業」に全国から5万床を超える手上げがあったことに触れて、「日本にはベッドがたくさん余っている」と主張している。しかし、5万床超もの手が上がった背景には、物価高騰や診療報酬の引き下げ、医師・看護師などの人員確保が困難になっていることなど病院の厳しい経営状況があり、決して「余剰病床」ではない。
精神病床を削減すれば、認知症や精神疾患を抱えた困難な入院患者を地域で受け入れていくことになるが、地域での受け皿は整備されていない。厚労省の調査では入院期間1年以上の退院先の最多は、「他の病院等に入院」や死亡などとなっているのが実情であり、長期入院の理由としても「精神疾患の治療に時間を要するため」や「転院先、入所先、居住先が見つからない」との回答が多い。治療が必要で退院先も見つからない患者を地域に放り出すことになりかねない精神病床の削減は無責任と言わざるを得ない。また、一般・療養病床の削減では、在宅医療のバックベッドの役割を果たしている病床が少なくなり、高齢者に多い肺炎や尿路感染症等ですぐに入院できなくなるという事態も懸念される。
さらに今年は団塊の世代が全て75歳以上になる年であり、入院医療のニーズは今後さらに高まる。病床が削減されることで看護師などのスタッフも削減されることになるが、減った人員は一朝一夕に増やすことはできない。政府は、入院ではなく在宅での療養を推進しているが、特に都市部では高齢単身世帯が多い、家屋が狭いという特徴があり、訪問介護を必要とする人が多いにもかかわらず、訪問介護は報酬削減により倒産が相次ぐなど危機的な状況にあり、現状、地域の受け皿が整備されているとは到底言えない。感染症の拡大や災害などの非常時対応が脆弱になることも火を見るよりも明らかである。
こうした現状を招いた政策を省みず、これ以上の病床削減を大規模に進めれば確実に医療崩壊に陥るだろう。特に大阪は、コロナ禍で何度も医療崩壊の状態に陥り、高齢者・介護施設で感染者が出ても入院ができず、施設内で留め置かれるケースが多数発生し、新型コロナウイルス感染症による都道府県別死亡率(人口10万対)は1位であった。にもかかわらず、数字ありきの議論を大阪が発祥の日本維新の会が先導していることに驚きを禁じ得ない。
医療提供体制を崩壊させないためには、平時からの余裕を持った病床運営ができるよう、人員確保につながる診療報酬の抜本的な引上げなどの対策が必要不可欠である。病床機能の転換や収斂は、地域の医療ニーズを踏まえた丁寧な協議の下で行うべきだ。機械的な推計や、ましてや医療費削減のための数値目標の設定などは言語道断であり、医療費削減のために病床削減の数値目標を定めるやり方に断固抗議するとともに、方針の撤回を強く求める。
2025年6月10日
大阪府保険医協会
政策調査部長 斉藤 和則
お問合せ/大阪府保険医協会
大阪市浪速区幸町2-2-20-401 電話06-6568-7721(担当=坂元・平井)