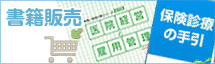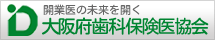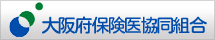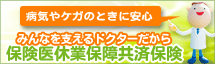斎藤緑雨
- 2019/3/5
- 作家寄席集め
作家寄席集め 第8回 斎藤緑雨/恩田雅和
 「明治二十三年八月二十二日」の日付を入れ、「正直正太夫死す」と読売新聞に自身の別号による死亡広告を出したのは、作家の斎藤緑雨(1868~1904)でした。時に22歳、その別号で「小説八宗」など発表し、文壇進出まもない頃でした。
「明治二十三年八月二十二日」の日付を入れ、「正直正太夫死す」と読売新聞に自身の別号による死亡広告を出したのは、作家の斎藤緑雨(1868~1904)でした。時に22歳、その別号で「小説八宗」など発表し、文壇進出まもない頃でした。
この一事からして、緑雨は若い時から書くものは反意的で皮肉にあふれ、随筆は警句を集合した趣になるほどでした。そのうちのよく知られたものの一つが、明治22年に書かれた「青眼白頭」所載の「按ずるに筆は一本也、箸は二本也。衆寡敵せずと知るべし」でした。
同様に警句集の様相を呈する明治30年の「おぼえ帳」について、緑雨と交友のあった内田魯庵は、「警句の連発に一々感服するに遑あらず」と述べています。その魯庵は緑雨に実際に会う前は、「正直正太夫という名からして寄席芸人じみていて何という理由もなしに当時売出しの落語家の今輔と花山文を一緒にしたような男だろうと想像していた」そうです。ところがその頃の緑雨は、「背の高いスッキリした下町の若檀那風の男で、想像したほど忌味がなかった」ようでした。
「おぼえ帳」には、落語家のことがいくつか記されています。「知らぬお方に三圓貰ひこれが御縁(五圓)になればいゝとは、一ころ落語家の繰返し唄へる所なり」。「とゞく(都々逸)る、ちやづ(茶漬)る、などいふは落語家より始まりしものなるべし」。いずれも言葉に関するもので、緑雨が寄席で耳にしていたことかと思われます。
緑雨の代表的な小説に、明治24年「国会新聞」に連載された「油地獄」があります。信濃出身の目賀田貞之進という主人公の学生は、嗜好を問われて、「寄席へ行けと云えば寄席へ行く、芝居へ行けと云えば芝居へ行く」と誘われたらどこでもついて行く男です。
ある日、長野出身者の集まりがあって、「余興とゝなえて伯円の講談」と「小さんの落語」を聞く機会ができました。しかし貞之進の関心はそこになく、この席で見かけた芸妓に向かい、いつしか女のもとに通いつめて金を使い果たした挙句に袖にされます。それでも諦めきれない貞之進はふと通りで見た二人連れ女の一人がその芸妓と思い、彼女が「落語が面白いと云ったことをおもい出して」、後を追いかけるように「立花屋という寄席」へ入ります。近くで見るとその芸妓でないことがわかり、貞之進は「高座で何事を云うか耳には這入ない」まま「寄席を飛出し」ました。
女に入れ込んだ若い男が身を持ち崩す典型的な花柳小説ですが、そこに二代目松林伯円、三代目柳家小さんという当時人気を博した講談師と落語家を実名で出し、寄席もあわせて舞台に登場させていたことは、作者緑雨がよほどそこに馴染んでいたことをうかがえさせます。
緑雨のもう一つの花柳小説「かくれんぼ」でも、二代目柳家小さんであった禽語楼小さんの名にチラッと触れてますし、これも警句集的な随筆「大いに笑う」には、小さんと三遊亭円遊の名が次のような例えで引かれています。
「人の一年を執りて一生を論じ去る如きは忘れても公平なる批評家のなすまじき事なり何が故に小さんたるや円遊たるやと言へば美人は悉く厚化粧なりと信ずる者は未浴後の美人あるを知らざるなり」
寸鉄人を刺す鋭い舌鋒を試みていた緑雨でしたが、肺結核に倒れて明治37年4月13日友人の馬場孤蝶に、「僕本月本日を以て目出度死去致候間此段広告仕候也」と口述筆記させました。それが翌日の万朝報に掲載され、最期までパロディ精神を持ち続けていた緑雨はわずか36歳の生涯を閉じました。